薩摩川内SDGsチャレンジストーリー(#25-1 樋脇地区コミュニティ協議会)
薩摩川内市では、令和3年6月8日に、市長が「薩摩川内市未来創生SDGs・カーボンニュートラル宣言」を実施し、2030年SDGsの達成と2050年カーボンニュートラルの達成に向けて取り組んでいます。また、令和4年5月20日には、国(内閣府)のSDGs未来都市に選定され、今後さらにSDGs及びカーボンニュートラルの達成に向けて、「薩摩川内SDGsチャレンジ」を合言葉に市民総ぐるみで取り組むことを目指しており、持続可能な社会の実現のために、「薩摩川内SDGsチャレンジ」を合言葉として、一人ひとりができることからSDGsの達成に貢献し、市民のみなさんと一緒に薩摩川内市の未来をつくる各種取組を実施しています。
各種取組の1つとして、市内でSDGsに関連する取組を行っている市民の方をインタビューした「SDGsチャレンジストーリー」を動画及びWebコラムにて公表しています。今回は、樋脇地区コミュニティ協議会の取り組みについて、会長の上床 博道さんをインタビューしました。
【関連ゴール】11 住み続けられるまちづくりを 15 陸の豊かさも守ろう


美しい丸山、樋脇川や市比野川の清流が流れる、薩摩川内市樋脇町。市中心地から山道を越えて樋脇地域に出ると、緑豊かな丸山の姿が目に入ってきます。お椀を伏せたようなその形は「本当にまんまるだなあ」と、見る人誰もが感じるのではないでしょうか。中腹には丸山自然公園があり、天然芝コート1面、人工芝コート2面を備える県内でも有数の運動場施設として、サッカーやグラウンドゴルフなど、子どもからお年寄りまで利用されています。薩摩川内市東郷町出身のサッカー元日本代表選手、前園真聖さんも小学生の頃、このグランドで練習や試合をしていたという縁から「前園真聖杯」が開催された実績もあります。

このように地域のシンボルとして親しまれている丸山ですが、遠くから眺め、公園を利用することはあっても、山登りについてはほとんど聞きません。丸山を登る人がいないのはなぜ?そもそも登れる山なの?その秘密を探りに、樋脇地区コミュニティ協議会を訪ねました。
「登ることはでけんどかい?」
迎えてくれたのは、樋脇地区コミュニティ協議会会長の上床博道さん、主事の久米俊朗さん。「こんなに丸い山はなかなかないですよね」と笑顔で教えてくれました。「記録をたどれば、昔から親しまれてきた山なのです。特に江戸時代以降は弁財天があり、牟礼川内丸山弁天とも呼ばれ、地域の人々にとって信仰の山でもありました。明治維新の廃仏毀釈により厳島神社へと改められましたが、山頂までお参りをしたり、いろんな行事をしたり、にぎわっていたようなんです」。
ところが、時代の移り変わりとともに山に登る人は少なくなり、神社が山麓に移されて参拝も下火になっていきました。ついには落石の危険性があるということで登山禁止となり、さらに平成25、26年ごろには実際に落石があり、通れない状態に。以降、そのまま放置されていたのですが、地域のなかに「やはり地域振興のためにも、地域のシンボルである丸山を中心に活性化していこう」という機運が出てきました。「話し合いのなかで、誰からともなく『登ることはでけんどかい?』という意見が出たんですよね」。





山に登り、遊んでいた頃をなつかしく思う地域の人たちもいました。「もう一回、ここを登れるようにしよう!」と丸山復活に向けて、プロジェクトが始動します。その名も「丸山フェニックスプロジェクト」。地域の人のべ500名が参加し、ボランティア活動により「丸山遊歩道」が完成しました。「みなさん手弁当で参加してくれた。これはもう大切にしないといけません。みんなの汗と苦労で出来た遊歩道ですからね」とほほ笑む上床さんと久米さん。「今後もさらに整備をすすめます。市から遊休地を借り受けて、あじさいを植えたり、遊歩道沿いの竹やぶを整地して、ツツジやモミジなど紅葉植物を植えたりする計画があります」と、まだまだ情熱は衰えません。「運動公園に加えて遊歩道も是非楽しんでもらえるよう、頑張っていきますよ」と熱く語ってくれました。心の拠りどころとなっている丸山だからこそ、こんなにも多くの人が協力し、整備することができたのだと感じます。
次回「薩摩川内SDGsチャレンジストーリー(#25-2)」では、植生調査の様子についてご紹介します。お楽しみに!
2023年11月取材
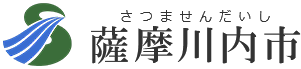







 メニューを閉じる
メニューを閉じる
更新日:2024年03月04日