薩摩川内市総合計画審議会[第3回] 会議録
1.開催日時
平成20年4月23日(水曜日) 10時00分~11時30分
2.開催場所
薩摩川内市役所本庁 601会議室
3.出席状況(敬称は省略)
[1]委員12名(欠席3名)
- 会長:黒瀬一郎
- 副会長:今藤尚一
- 委員:森薗正堂,谷口兼弘,三角文孝,田島直美,米丸恭生,橋口史人,下野千代男,徳田勝章,齋藤佐千子,伊地知すみ子
欠席:山元浩義,犬塚孝明,中村貴恵
[2]事務局等 3人
企画政策課:課長 末永隆光,課長代理 古川英利,主任補 諏訪原智子
4.会次第
- 会次第
- 会長あいさつ
- 議事
1.審議第3号 薩摩川内市自治基本条例原案について(第3章~第5章) - 閉会
5.配布資料
ダウンロード
6.委員から出された主な意見(要点・録音なし)
委員
第10条について,「多様な媒体の活用」というのは,高齢者の方には理解しにくい表現だと思います。「あらゆる伝達方法を用い」と表現を変えたらどうでしょうか。
事務局
「多様な媒体の活用」と「あらゆる伝達方法」という表現の意図は同じであると思いますので,検討させていただきます。
「媒体」というのは,市民の方がいろいろな情報を入手するためのホームページ,あるいは広報紙などを指しています。そういったものを活用して市民の皆さんは情報を得られると考えています。
委員
市民と市の情報共有というのは非常に大事なことで,情報共有することで市民はまちづくりに参画できると考えます。
そこで,第1項に新たに「市民と市はお互いに連携しながら情報共有に努める」というのを挿入して,順次1項ずつ繰り下げたらどうでしょうか。
事務局
まず情報共有という目的があって,その下に情報提供という手段があると考えます。御指摘の文言の挿入に関しましては,検討させていただきます。
委員
第10条の第2項について,情報の共有は,ワンサイドでは成立しません。「相互の情報収集」ということで,自分たちから出た情報なんだ,要望なんだということを目に見える形にすることが大事ではないかと考えます。
よく「公の文書が非常にわかりにくい」という意見を聞きます。できるだけ文章は簡潔に,文章に表せない場合は,注釈をつけるなど,一般の方にもわかるように工夫をしてほしいと思います。
事務局
情報共有という前提がある中で,情報が一方通行であってはいけない,双方向性を持たせなければならない,という御意見をいただきました。
検討させていただきます。
委員
我々も参画していくんだという意識を持つ意味でも大事なことではないかと考えます。
事務局
わかりやすい情報提供というのが第一だと考えます。
意見交換会で広報紙に対しての意見が多く出されました。そのような意見を受けて,今年度から広報紙を見直し,分かり易い紙面に変えていこうとしています。
まちづくり意見交換会で出された意見を参考に,変えていこうという取り組みがあります。
委員
第10条第3項の「多様な媒体の活用」という表現について,「総合的な情報提供の体制整備に努める」という部分にすべて網羅されていると考えるので,高齢者の方に対してはこの部分で理解を得られると思います。
委員
第14条第2項「市民がまちづくりに参画しないことによって不利益を被ることのないように配慮しなければならない」とあります。この部分は,自分の権利だけを主張し,自治会等に参画しない傾向を助長するのではないでしょうか。
事務局
第2項に関しましては,庁内の中でもさまざまな議論がなされたところです。外の委員の方も御意見をお寄せいただければと思います。
委員
今の意見に同感です。これを敢えて書けば,参画しない原因になるのではないかと思います。
参画の手法はいろいろあります。(自治基本条例には)罰則もないわけなので,敢えてここを入れる必要はないのではないでしょうか。
委員
同感です。これは,基本条例ですので,やはり歯止めは必要だと思います。
委員
一般的な意見というのをここで申し上げておきたいと思います。まちづくり意見交換会,出前講座等に出席された方々の人数が,全体の何%であるか,市としてどのような認識をお持ちなのかを考えています。
働く世代は労働が中心であり,子育て世代は学校が中心になります。そこを(参画にあたって)ご配慮いただくと,魅力的なまちづくりができるのではないかと考えます。
市境にいらっしゃる方には,薩摩川内市を選んでほしいと願っています。そのための条例づくりであってもいいのかなと考えます。
そのようなことを考えると,第2項は,全体を見回したときにバランスが取れていると思います。むげに削除するのはどうでしょうか。
委員
第2項は,必要ないと思いました。
その代わり,第1項を膨らまして,参画する場所を提供するという意味合いを挿入し,参画を保障することに重点を置いた条文に修正したらどうでしょうか。
委員
同感です。まちづくりに参画したい,やりたいという気持ちがあればいつの機会を利用しても参画できるということを,どちらかというと提言する方がいいと思います。
そのような文言が入るのであれば,この第2項は再検討してもいいと思います。
委員
市民参画がこの条例の一つの趣旨の中で,参画しないことを保障する条項を入れること自体どうでしょうか。
委員
あの人は参加しない,ということで排除の枠を設けたら本末転倒だと思います。既に存在する組織などにおいて力関係がはっきりしていれば,新たに入っていけないと感じる人もいます。
事務局
再度市民参画を促進する,促すような条文になるように検討したいと思います。第2項の削除の有無も含め検討し,前向きに考える方向に表現を変えて行きたいと思います。
委員
未加入者問題に対しても,これは入ってみようかな,という気持ちになるような,文章になるよう検討していただきたいと思います。
委員
第13条第2項において,市民だけが公共的課題の解決や公共的サービスをするというニュアンスを感じ取れなくもない。
「市民がその担い手となれるよう」というところを「市民と市が一体となって取り組めるよう」という表現に変えたらどうでしょうか。
委員
同感です。公共的サービスを市民が担うとなると,では職員の立場はどうなのかと思います。市の職員がメインで,市民がサポートをする場面もあるかもしれません。主体的に市民が公共的サービスの提供とか公共的課題の解決とかいうのは無理があるのではないでしょうか。
事務局
表現に関しては,検討させてください。
市民の中には個人もNPOも事業者も含まれますので,公共的課題の解決や公共的サービスの提供は個人だけが行うものではありません。
公共的課題の解決や公共的サービスの提供というのは,今まで行政だけでやってきましたが,現在,法律の改正,社会潮流等の変化があって市民の方々も一緒にやっていきましょうということになっています。そこで,適切な措置,配慮もなしに市民に一方的に押し付けることのないよう,挿入した項でした。
委員
そのような趣旨は,理解できます。ただし,ニュアンス的に誤解を生む危険性もあるのではないか,と感じましたので発言いたしました。
委員
第16条,第17条はいいと思います。今まで,いろいろ要望しても梨のつぶてということもあったわけですが,最近では,様々な情報をもとに回答されています。以前なかったこのような態度をきちんと規定されるのは,良いことだと思います。
第18条について御意見を申し上げます。パブリックコメント手続実施要綱には,「出された意見の尊重」ということが書かれてあります。そこで,この条文の中にも挿入したらどうかと思います。
事務局
パブリックコメント実施要綱第2条に「出された意見を考慮して,本市としての意思決定を行う」,あるいは,第7条に「実施機関は,提出された意見を考慮して計画の意思決定を行うものとする」とあります。先ほど「尊重」と言われましたが,「考慮する」と言う表現と一緒なのかどうかも含めて検討したいと思います。
意見を求めるだけでなく,考慮して採択するしないを決め,採択されなくても市の考え方を示すと,いうことでもう少し工夫して第18条の中に入れたいと思います。
委員
第17条に関しての意見です。クレームを受けるのは,主に職員の方だと思います。個人を攻撃したり,公共の福祉に反する意見・要望・苦情対応については,この条項から排除したいということですが,職員の精神衛生を考慮すれば,それは入れるべきではないかと思います。
それから「意見・要望・改善・苦情の内容の公開」ですが,これは個人情報とも絡んで公開しない方がいいのではないかと考えました。
意見,要望を言う側は,冷静さに欠いていることもありますので,あとで後悔することもあると思いますので,公開するのはどうだろうかと考えます。
事務局
第17条についてです。「個人を攻撃したり,公共の福祉に反するような意見・要望・苦情について排除したい」と事務局としては思っていますが,外の委員の方のご意見も伺えればと思っています。
「意見の内容は公開するべきか」という点について,公開しない方がいいというご意見でありました。意見の出し方は様々で,きちんと手紙やファックスで住所・氏名を書いてこられる方もいます。また,匿名の方もいます。
このことについても,外の委員の方の御意見を伺えればと思います。
委員
第17条第1項ですが,このままだとこの条文を盾にとって様々な意見等を言ってくる方もいると思いますので,ある程度歯止めになるような表現を入れておいたらいいのかなと思います。そのような表現が入っていたら,そのようなものは受け付けませんということで,跳ね返すことができると思います。
第15条の方に戻りたいのですが,第15条は参画への配慮ということで第14条の内容を反映したものだから,いいのではないかと思いました。
委員
出された意見で,きちんと名前を出している,内容もはっきりしているという場合には,自分の意見を吸い上げてほしいという思いがあると考えます。そういったことを考慮すれば,公開すべきかどうかというのは,本人に選べるようにしていたらどうでしょうか。
委員
公開の件ですが,名前は出さず,意見とそれに対しての回答というものを,個人攻撃とか公共の福祉に反する意見,要望,苦情等といったものを排除した上で,建設的な意見は公開するべきだと思います。
統一的に公開するということ,名前は出さないというものさしで対応したらどうでしょうか。
委員
第16条の「対話の場の設置」に対する意見です。
これについては,中学校単位で行うという説明がありました。この条例は,市民参画を促し市民の意見を吸収しようという趣旨の中で,取り組んでいるものだと思っています。
これから,学校も統廃合されて取り残される地域というのも出てきます。しかし,そういった地域に対してもやはり重点的に目をかけていかなければ,薩摩川内市全体のまちづくりは成り立っていかないだろうと考えています。そこら辺を考慮してこの出前講座等の進め方に対しての具体的な方針を今後出していただけたら,と思います。
事務局
対話の場の設置では,例として「ふれあい市民会議」を取り上げ,その中で中学校単位というのを説明させていただきました。
この対話の場の設置ということを,この条例でうたって,その運用については市長が決める。その運用をこの条例の中で具体的に盛り込むことは出来ないでしょうけれど,職員が出向いていって様々な説明をする,意見交換をするという細かな対応は,今後もできるのではないかと思っています。
委員
この基本条例は,市長が出向いて話を聞くということを変えてはいけないから,それを踏襲していこうということで検討されているものだと考えています。そこの含みのある条例の制定だとすれば,小規模の地域にも目をかけるような配慮をしていただきたいと思い,意見を述べたところです。
事務局
第17条に関しましては,2つ大きな論点があります。公共の福祉に反するような意見等の取扱い,それから意見等の公開です。
庁内議論で,これらを入れるべきか入れないべきか,という話が両方ありました。先ほど第14条第2項で,不利益の取扱がありましたけれども,それと同じように具体的すぎるのではないか,という意見も出されましたのでここで論点として挙げさせていただいたところです。
出されました意見を参考に,再度お諮りしたいと思います。
意見等の公開につきましても,運用の基本的な方針も含めて原則公開という方向で,もう一回確認事項とさせていただきたいと思います。
審議会終了
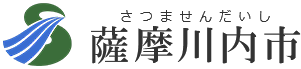







 メニューを閉じる
メニューを閉じる
更新日:2023年03月27日