薩摩川内市総合計画審議会[第4回] 会議録
1.開催日時
平成20年5月13日(火曜日)10時00分~12時00分
2.開催場所
薩摩川内市役所本庁 601会議室
3.出席状況(敬称は省略)
[1]委員12名(欠席3名)
- 会長:黒瀬一郎 副会長:今藤尚一
- 委員:森薗正堂,谷口兼弘,三角文孝,田島直美,米丸恭生,橋口史人,下野千代男,徳田勝章,齋藤佐千子,伊地知すみ子
欠席:山元浩義,犬塚孝明,中村貴恵
[2]事務局等 6人
- 企画政策課:課長 末永隆光,課長代理 古川英利,政策グループ長 有馬眞二郎,主任補 諏訪原智子,主任補 山元一将
- コミュニティ課:課長 前平照幸
4.会次第
- 会次第
- 会長あいさつ
- 議事
- 審議第4号 薩摩川内市自治基本条例原案について(第6章~第9章)
- 閉会
5.配布資料
ダウンロード
6.委員から出された主な意見 (要点・録音なし)
委員
第20条に関しては,これでよろしいと思います。
第21条第1項に関して,コミュニティ協議会は既に活動を始めて4年目に入っています。そこで,「組織し,」という表現を敢えて条文に用いなくてもいいのではないでしょうか。合併協議の中で位置付けられた組織でもあるし,地区名も固定されています。また,いろいろな補助金等についても議会を通じて予算化されて配分されているわけですので,この表現は不要でないでしょうか。
第22条についての意見です。「環境整備」という表現では分かりにくいので,もう少し具体的に表現してもいいのではないでしょうか。
第23条です。「相互扶助」という言葉は,福祉的な守りの姿勢をイメージします。そこで,なぜ自治会に加入しなければならないか,という前提として「お互いに市民の権利と責務を果たすということ」「共生協働で取り組む」といったことを盛り込んだらどうでしょうか。
事務局
第1点目の「組織し,」というところです。今,既に48地区コミュニティ協議会が設立されて4年目に入っています。順調に運営がされているところですが,その規模は様々です。少子高齢化も進み,地区コミュニティ協議会の運営自体も厳しい状況にあるところもあると聞いております。そこで,今後の動きとして,地区コミュニティ協議会の合併ということも考慮し,「組織し,」という表現は外せないだろうということで検討してまいりました。しかしながら,「運営する」という文言ですべてを含むというご意見もありましたので,再度検討したいと思います。
「環境整備」の部分は,非常におおまかな表現,抽象的な表現でまとめてあります。地区コミュニティ協議会に対する支援というものが様々あるんですが,もっと分かりやすく具体的にということであれば,もっと表現を検討してみたいと思います。
「相互扶助」の表現ですが,積極的なまちづくりへの参加,市民が実際に加入したくなるような表現に変えられないか検討してみたいと思います。ただし,相互扶助という言葉は,古い言葉ですが,助け合いの精神であり,やはり自治会の中では最も大事なところであると思います。そこで,これに加え,新しく積極性を前面に出せる表現がないか検討してみたいと思います。
事務局
地区コミュニティ協議会の名称について先ほどご意見がありました。この名称については,小学校の名前が地域に密着していて,範囲が分かりやすいのではないかということで,お奨めした経緯があります。ただ,上甑地区のように小学校名を地区名として採用していないところもありますので,小学校名イコール地区名というわけではありません。
委員
地区名に関しては,議会でも議論されて通っていると認識しています。だから,今ある地区名を別の地区名に勝手に変えられないはずです。そこを確認していただきたい。
事務局
合併協議時は,小学校区を基本に地域の方から意見を聞いて,名称を決定したところです。地域の方で地区名の名付けをしていただいて,議会では社会教育法上の公民館はどのような名称にするかということで議論がなされたと記憶しています。
現在は,地区単位の公民館は廃止されていますので,地区名を固定化する例規はないと考えています。
地区名の変更を検討されるのであれば,その辺の経緯を確認したいと思います。
委員
第21条は,地区コミュニティ協議会はいろいろな予算措置を含めて,市や市議会からきちんと公認されている協議会なので,今更「組織し,」という表現は必要ないのではないか,ということです。
先ほど合併の話をされましたが,そのような問題は自治会にもあるわけです。であれば,第23条にも「組織し,」という表現を入れないといけないと思うわけです。
委員
「協議会を組織し,」という表現は,今後この組織を活用していくという観点でこの条例の中で整理されていると思うわけです。なので,固定する文言で表現したらどうかな,と思うわけです。
第21条の第2項ですが,わたしは,第1項と第2項が重複している気がしますのでいらないのではないか,と考えます。
第23条の自治会活動への考え方ですが,「相互扶助に基づき形成された」というのは,言葉では非常に柔らかい文言ですが,やはり協働活動に参画することを促すような文言として強調したほうがいいのではないでしょうか。
ここの文言は,第14条と結びつきが強いと考えます。できれば,積極的な文言に変えていただければと思います。
委員
第23条に関しての意見です。第23条と第14条は,非常に結びつきの強い条項だと感じました。
そこで,思うのですが,自治会への未加入者の状況を把握しているのかということが1点あります。
宮崎市を例にとると,コミュニティ税の導入があります。コミュニティ税とは,各世帯から税として徴収するというものです。その税の使い道は何かというと,参加しない人の不足分を補い,また限界集落への補助にもあてていきます。これは,市民と議会に対し,市は説明に説明を重ねて全体の意見がようやく得られて条例化されたものです。それを踏まえて,この第23条はそこの布石になるのかなと感じたわけです。
相互扶助の精神と言うことに対して,もっとみんな積極的になってほしいということでこの条例を考えたのかなと思いました。
事務局
意見交換会の中で,地区コミュニティ協議会と自治会との関係を問う意見がありました。最初は,協力的な地区内の団体と地区内の団体が協力してくれない,というところもあって温度差がありました。今,4年目を迎え地域の一体性はできつつあると思いますが,そのような現状も踏まえ,互いに連携しましょうというのをあえて入れさせていただいたところです。
委員
現在,地区コミュニティ協議会に参画していない自治会はあるのですか。
事務局
今はないかと思います。
委員
地区コミュニティ協議会と自治会のつながりの度合いは,各自治会によって差異があります。自治会長も地区コミュニティ協議会で役職についていただいているわけですが,1年交代が多く,コミュニティ活動そのものに対する理解ができつつあるときに辞められるという事実があります。
第1項は,組織づくりであって,第2項は,組織されたものがどのようなつながりをもって,コミュニティ活動を展開していくかという捉え方ができますので,この項はあっても支障はないのかなと思います。
委員
地区コミュニティ協議会は組織されて4年を迎えようとしていますが,つながりはその年々で切れてしまって大事なことが津々浦々まで浸透していない,理解されていないということが多々あります。
これからは,地区の方に協議会組織とか自治会とかいうものを事あるごとに説明し理解をしていただくことが重要ではないかと思います。外からの努力も大事ですが,地区住民に意識改革も必要だと感じています。
それから,第22条の「環境整備」という表現です。条文ですので,事細かく文章化するというのは難しいかもしれませんが,若干許される範囲で,このような内容というのがわかるような文言は出した方がいいのかもしれません。
委員
地区コミュニティ協議会も4年目に入り,まだ途上にある。これからが正念場であろうと感じています。その様な観点からも,第1項の主体は,「市民」で第2項の主体は「協議会」になっているので,このままでもいいのではないかと思います。
委員
第21条の第1項,第2項に関しては,それぞれ主体が違うからこのままでもいいのかなと思います。
第1項については,先ほどから申していますように「組織し,」と書けば,「じゃあ組織しなくてもいいのか」ということになる。ここに敢えて「組織し,」という文言を入れるのであれば,第23条の自治会にも入れないといけない。
自治会も地区コミュニティ協議会も同じ任意組織なのだから。
事務局
「組織し,」というのを無くした場合,どのような表現になるのか検討させていただきたいと思います。
委員
表現に関して意見があります。
第22条2項です。「損ねる」という表現がありますが,マイナスイメージの強い言葉ですので,同じ意味であれば「尊重し」という言葉がいいのではないでしょうか。
第22条第1項です。「環境整備」という言葉が先ほどから出ていますが,ここはできるだけ柔らかく「適切な環境を整える」という表現にしたらどうでしょうか。
それから第23条です。「形成された」という表現です。簡単に「つくられた」「組織された」と表現するほうがよろしいかと思います。
第24条で「支援することができる」というのは,通常の文章でしたら違和感はないのですが,条例の中では,「支援することができるものとする」というぐらいに重みをもたせた方がいいのかなと思いました。
事務局
表現に関しましては,地区コミュニティ協議会,自治会両方のバランスを考えて,検討したいと思います。
第23条のところで出ました,コミュニティ税の導入,加入率の話であります。加入率は把握しています。
コミュニティ税の導入ですが,自治会活動を支援するために新しい法定外普通税を導入する考えは一切ありません。従来の自治会活動の中で,会費を納めていただいて自治会活動はそれでやっていく,それに対して市として支援をしていくというのが,第24条にあるとおりです。
「相互扶助」に関しては,もう一歩踏み込んで,共生協働を促すような表現を改めて検討したいと思います。
委員
第22条第1項の「環境整備」は,この条項の見出しと同じように「支援」と切り替えるほうがいいと思います。
委員
第23条についての意見です。コミュニティ税を導入する考えはない。あくまで,市民のみなさんの意思で運営されている活動に支援するということはわかりました。
加入状況はどうなんでしょうか。
事務局
4月1日現在の状況です。市全体では,83.7%です。川内地域が80.3%,一番高いところで上甑地域の99.2%です。傾向として,やはり地方に行くほど加入率は高くなっています。
委員
運営が厳しいという状況は,どういった点から厳しいのでしょうか。
事務局
地方の方では,若い人たちがどんどん出て行って,帰ってこなくなる。高齢化が進んで,運営そのものが出来なくなる地域があります。
中心部でいえば,例えば一人世帯の高齢者,若い方は共稼ぎが多く,なかなか役員が出来ない。そのことが負担となって自治会に入らない。そういった事情もあります。
委員
住民の意思も尊重されているとわかりました。ありがとうございました。
委員
第25条で,「自治基本条例」があって「総合計画」があり,「総合計画」があって「各事業」がある。そして,財政運営がある。というのがわかってよかったと思います。
第28条です。「権利利益の保護」とありますが,「権利及び利益」としたらどうなのかなと思いました。権利と利益は意味的には別々なのではないでしょうか。
事務局
同じ条項に「行政指導及び届出」とか「公正の確保及び透明性の向上」という文言もありますので,検討させてください。
委員
第29条の「市民投票」についての質問です。この数字は,地方自治法を根拠にしていることがわかり,理解しました。
3月1日付け発行「議会だより」において,江口議員の一般質問で「市民投票制度を盛り込んだらどうか」という質問に対し,市長は「本市としては,民意の反映は議会を優先する。住民投票制度は消極的に解している」とありますが,その意味について教えてください。
事務局
平成19年12月議会の一般質問であります。
12月議会の時点では,自治基本条例の骨子に「市民投票」の条項は無く,そのため議員から入れるべきだという質問をいただいたところです。
この段階で市長は,地方自治法の中に規定しているものを敢えて条例でうたう必要はないというスタンスで,「消極的に解している」という表現で答弁されました。
その後,48地区での意見交換会,パブリックコメントの中でやはり入れるべきだという意見が市民から出されましたので,庁内で会議をいたしまして,これはやはり入れた方がいいだろうという結論に達し,原案に盛り込んだところです。
市民投票制度は,直接民主主義であって,議会というのは間接民主主義です。市長の立場としては,最終的には間接民主主義,議会の意向を尊重したいということで12月議会で答弁しておりますし,その考えは今も変わっておりません。
委員
第8章・9章の論点をもう一度説明してください。
事務局
論点22は,審議会につきましては,第19条で原則公開をうたっているのですが,この条項でも敢えて盛り込む必要があるかということ。
論点23は,審議会の開催の目安をこの基本条例できちんと規定する必要があるかということです。
委員
基本的にはこのままでいいかと思います。第2項についても第19条で原則公開をうたっているので,ここで敢えて盛り込まなくてもいいのかなと思います。
事務局
我々も論点で挙げさせていただいていますが,内容的には細かいかなと思いますので,規則に委任することにします。
委員
第22条第2項で「役割を認識し,」という表現がありますが,いただいた資料を見ても,この地区コミュニティ協議会の役割というのが,掲載されていませんので,ここの表現はどうなのかなと感じます。
第29条ですが,どうしたらできるという手続論だけで,出された結果には触れていないのですが,そこのお考えはないのでしょうか。
事務局
第22条第2項に関しましては,市の立場から見た役割と市民の方々から見た役割があると思いますので,改めてそこをもう少しわかりやすい表現ができないか再度検討させてください。
第29条に関しましては,手続的なものをこの中に盛り込んであります。
出された結果につきましては,直接民主主義と間接民主主義のどちらを尊重するのかということに尽きると思います。住民投票の結果がベストなのか,議会の意思がベストなのか,市長の意思がベストなのか,その辺は最終的に議論されるわけですが,今の法体系でいきますと,議会民主主義を取っておりますので,やはり議会の意思を尊重しなければならないということになります。
住民の皆さんの意思は参考になりますけれども最終的な決定ではない,ということをどこの自治体でも取っていますので,ここでは敢えてその部分は触れておりません。
委員
そうなってきますと,その条項は意味があるのでしょうか。
事務局
薩摩川内市の最終意思決定は,地方自治法上では議会の決定です。ですので,この自治基本条例では,そこまで踏み込まずに手続論だけを挙げさせていただきました。
委員
第21条の「組織し,」という文言は,私の考えでは必要ないと思いました。
事務局
今まで説明をした通り,合併後導入した地区コミュニティ協議会制度は,当初48地区でスタートしましたけれども,これが永遠このままで行くかと言うとそうでもないと感じています。社会情勢の変化があれば,合併するところも出てくるということも想定して「組織し,」という表現を敢えて用いたところです。ただ,そうなると自治会とのバランスも出てきますので,そこは検討させてください。そこの部分は次回説明したいと思います。
審議会終了
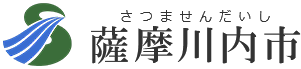







 メニューを閉じる
メニューを閉じる
更新日:2023年03月27日