薩摩川内市総合計画審議会[第5回] 会議録
1.開催日時
平成20年6月3日(火曜日) 9時30分~11時30分
2.開催場所
薩摩川内市役所本庁 601会議室
3.出席状況(敬称は省略)
[1]委員11名(欠席4名)
- 会長:黒瀬一郎
- 副会長:今藤尚一
- 委員:谷口兼弘,三角文孝,田島直美,米丸恭生,橋口史人,下野千代男,徳田勝章,齋藤佐千子,伊地知すみ子
欠席:森薗正堂,山元浩義,犬塚孝明,中村貴恵
[2]事務局等 4人
企画政策課:課長 末永隆光,課長代理 古川英利,政策グループ長 有馬眞二郎,主任補 諏訪原智子
4.会次第
- 会次第
- 会長あいさつ
- 議事
- 審議第5号 薩摩川内市自治基本条例原案 修正案について
- 閉会
5.配布資料
ダウンロード
6.委員から出された主な意見(要点・録音なし)
前文~第1章
委員
全体的に審議会の意見を踏まえ,それなりに修正していただけたと思います。まず第1章からですが,第4条に「最高規範」という文言が挿入されると,権威があるなと感じます。
私の方からは,特に意見はございません。
委員
委員の方たちの意見を踏まえながら,非常に適当な修正が行われていると思います。基本条例に必要な条項もうまく関連付けられています。このままでいいのではないか,と思います。
委員
私も今の2人の委員の意見と同様です。素晴らしくきめ細やかにまとめてあると感じました。
第2章
委員
第2章第9条「職員の責務」でお尋ねします。
市民と職員で今後のまちづくりは行って行きましょう,という意図は強く伝わってきます。ただ,何か最終的な決定とか,このようにしましょうという最終的な責任の所在というのは,どこにあるのでしょうか。
事務局
ここの第9条の「職員の責務」は,職員自体の自己責任の部分と捉えています。今,おっしゃったような「責任」ということになりますと,すべて第7条の「市長」のところにかかってきます。
そこで,市長を「市政経営の最高責任者」と表現しているところです。
委員
市長が,市の運営の最終決定,最終責任者というのはわかります。権限も集中している,というのもわかります。
ただ,実際,現場で「これは市長が決定します。市長の責任です」と言われるとどうなのかな,と思ったわけです。
委員
「責任の所在」ということですが,一緒にまちづくりを行いながら中には責任転嫁をする職員もいるのではないか,という懸念も含まれているのですか。
委員
そのような意味も含まれます。それにプラスして市の職員は,労働時間が8時間勤務と決まっていても,公人または私人という線引きがなかなか難しいと思います。
そこで,「奉仕」という言葉を用いることによって,24時間公人というイメージがつき,それによって職員は拘束されるのではないか,と考えてもいます。
事務局
職員の身分の保障,あるいは常日頃の行動については「地方公務員法」というのがあって,その中で規定されています。また,「全体の奉仕者」ということも,憲法第15条にもうたわれています。
職員は,公務員という立場で24時間拘束されるところもありますし,退職した後も守秘義務とかそういった部分は,制約を受けています。
職員の責務,責任といった言った部分は,広い意味では,第1項の「全体の奉仕者」の部分,「効率的にその職務を遂行しなければならない」という部分で捉えることができるのではないかと考えます。
委員
「責任逃れ」の部分についてはどうでしょうか。
事務局
職員一人ひとりの権限というのは,市長から順次下ろされたものなので最初からあるわけではありません。ただ,「全体の奉仕者」という意識を持って職員は採用されますし,宣誓もします。
社会的,道義的責任という言い方をしますと,当然職員としての資質であるとか,市民に対する接し方であるとか,職務に対する社会通念上の責任というのは当然あると考えます。
委員
やはり,この条項の要の部分は,積極的に市の職員として,まちづくりを支援していくまちづくりに関与していくという精神だと考えています。「責任逃れ」の部分に関しては,事務の流れの中で日々解決していかなくてはいけないものではないかと考えます。
委員
第8条の執行機関の責務の中に「市の執行機関は,その権限と責任において」という表記があります。やはり,職員のいろいろな業務についてもこの「権限と責務」に含めていいのではないかと考えます。
委員
やはり,職員自らがプロ意識を持って職務を遂行することは大事なことだと私は思います。その内容が,この条項には網羅されていると思いますので,このままでいいと考えます。
委員
市町村合併を行った後の地域住民というのは,職員の知恵・指導をいただきたいと思っている。そして,時には足かせになろうかと思いますが,時間外でも地域のために力になってくれ,という願望がある。
そのようなことを考えると難しい表現になるわけですが,それが,「全体の奉仕者」に包括されているという考え方でいいのではないですか。
委員
住民サイドからの意見でひとつ。地域にどうしても垣根があります。それを取り除くために,私たちは,自分たちの薩摩川内市の改革,行政がどのようなまちづくりに取り組んできているのか,ということをもう一度考えながらコミュニティの活動を行っております。
人数が減ったらどうすればいいのか,みんなで力を合わせる以外ないでしょう。昔もそのようにやってきたでしょう。それが今無くなりつつある。それをもう一回元にもどしましょう,と。そして力を合わせて行動しましょう,ということを常々話しております。
行政は,専門家ですので,厳しい指導があって然りだと思います。それはそれで,頑張ってもらわないといけない。
しかし,住民もやはり,「市民としての責務」を果たさなければならない。そこで住民に「市民の権利及び責務」とこの「職員の責務」の部分を理解してもらうことが大切だと考えます。この条項の部分は素晴らしいな,と考えます。
委員
私は,行政と市民で協働してまちづくりをしています。こちらの「職員の責務」を見ますと4項目に分かれていて,職員の方のことがしっかりと書かれておりますのでとてもありがたいと思います。
委員
いろいろと意見が出ておりますけれど,第4項に書かれておりますように,職員も地域社会の一員であることを自覚してまちづくりに取り組むんだ,ということをしっかりと細部まで行き渡らせてほしいと思います。
第3章
委員
第10条の「情報の共有」に関しての質問です。
「市は,その保有する情報を市民に分かりやすく提供し,」とあるのですが,誤解は生じないのでしょうか。
「その保有する」となったときに,情報共有が出来るものと出来ないものがあるということを明文化しなくても大丈夫なのでしょうか。
事務局
ある程度限定する形の表現も検討したのですが,既に情報公開条例というのが定められています。その条例の中に,個人情報も含めて公開できる部分,あるいは伏せて公開する部分などが規定されております。
委員
そうであれば,「情報公開条例に基づき」とか,そういう文言があるほうがいいのではないでしょうか。
事務局
他の条例との関係で言えば,この条例は最高規範なので,一番の基本になります。自治基本条例に基づいて,情報の提供をする場合は,「情報公開条例」とか「個人情報保護条例」とか,下の条例で整理されるということになります。
委員
市民の方に誤解が無ければそれでよろしいかと思います。
第4章
委員
第4章第13条第2項です。「市民がその担い手となれるよう」という表現があります。ここは,修正しないということで,下に【理由】があります。言われようとすることは,この【理由】を読めば分かるのですが,ここの部分は抽象的な表現で市民には分かりにくいのかなと思います。もっと一般的な表現に変えたらどうでしょうか。「市民が主体的に活動できるよう」,という表現でもいいのはないかと思いました。
事務局
この部分は,非常に難しくて議論したところです。
第2項だけ見れば,「市民が主体的に活動できるよう」ということかもしれません。ただ,前提として第1項があります。
第1項で,市民と市が一緒にまちづくりをやっていく。第2項で,その際市の方は,市民の皆さんが,ちゃんと活躍できるように,担い手となれるように適切な措置を講じましょうという意図です。
委員
また,検討していただければと思います。表現の問題だと思います。
第5章
委員
第17条「意見等への対応」のところです。意見を集約していただいてこの文言になったということで,ずいぶん分かりやすく伝わりやすくなったと思います。
そこで,出された意見の取扱ですが,「必要に応じて公表する」とあるのですが,「必要に応じて」の判断基準はあるのですか。
事務局
意見,要望,苦情等の対応メモは,公文書に該当するかと思います。そうなりますと,情報公開条例,個人情報保護条例という条例の適用を受けると考えます。そこで,公開する部分と非公開の部分と整理できると考えます。
委員
第18条「市民意見の公募手続」です。
「市は,本市の基本的な計画,構想等を策定しようとする場合には」とあります。今まで市サイドで決定していたものまで市民参画ということを考えているのですか。
事務局
ここでは,いわゆるパブリックコメント手続について述べています。基本的には総合計画以下の個別計画に限定しようと考えています。
そのほかに,市民生活に大きく影響を与えるような計画に関しても,リクエストがあれば意見として公聴機能を活用して,そちらできちんと意見を聞いてパブリックコメントをするかしないかを判断し,市民参画を進めていこうと考えています。
委員
そうなりますと,今後の市政運営というのは,市民参画ということが大前提となるということですね。
事務局
そのようにしていきたいと考えています。
ただ,運用の問題があって,意見の聞き方,タイミング,締め切りなど事務を進める上で,庁内で周知徹底をする必要があります。
第6章
委員
平成17年度にコミュニティ協議会を発足いたしまして,地区振興計画をつくりました。そして,総合計画に反映していただいたり,支援をいただいております。この地区振興計画について今後,どのようになるのか,そこのところをお聞きしたい。
事務局
総合計画の上期計画,平成17年度から平成21年度までの5ヵ年計画ですが,その中で,48地区コミがつくられた地区振興計画を反映して参りましたし,予算の状況に合わせて予算付けをするとか,そういったこともやってまいりました。
これから平成22年度から平成26年度までの下期計画を立てなければなりません。その場合に,地区コミが策定します地区振興計画は総合計画の基礎的なものであると位置付けをしております。
委員
そうであるならば,第22条か第25条のところに,「地区コミュニティ協議会が地区振興計画を策定し,それを市が支援する」という文言を挿入してほしいと思います。地区コミュニティ協議会もそうですが,地区振興計画も位置付けて,市が支援することを明記する必要があると考えます。
それこそ,トップが変わると取扱が変わる,ということでは困りますので。
事務局
他の委員の方のご意見も拝聴したいと思います。
位置付け的には非常に重要なものであると認識していますので,検討してみたいと思います。
委員
総体的に全く同じ考えを持っております。地区の活動というのは,地区振興計画が根元にあります。やはり,その活動を着実にものにしていきたいという視点からも,この条例に挿入が可能なら入れていただきたい。
委員
今まで出された意見と同じですが,地区コミを立ち上げて4年になります。トップが変わろうがどうしようが,やはり地区コミュニティ協議会としての活動が展開できるような最低限の保障というものが,この条例の中にほしいと思います。
事務局
いろいろと御意見いただきました。地区コミュニティ協議会制度は,合併後,薩摩川内市が選択した制度で全国からも注目を浴びているところです。
地区コミュニティ協議会が,今ある課題を整理してまちづくりの方向性を示した地区振興計画の位置付けというのは大事なものであると考えます。
市のまちづくりとの関連において非常に重要な位置付けだと思いますので,次回報告させてください。
委員
コミュニティの力というのは大事だと考えますので,その辺の部分も十分検討してください。
全体を振り返り
委員
最初に戻っていただいて,前文の一部です。4段目の「それぞれの役割」の「それぞれ」が気になります。「その役割」でもよろしいのではないでしょうか。濁音が入ってくると,少し耳障りに感じます。
事務局
「それぞれ」は「市民と市」を指します。
委員
市民と市の関係を柔らかい別の表現で変えた結果なので,このままでいいのではないですか。
前の部分との比較で理解していけばいいと思います。
委員
今回の訂正で,「市民と市がお互いを尊重しながら」と修正していただいたので,「その役割と責務」でも十分意味は通じるのかなと思ったんです。
事務局
第2条第6号「協働」の説明で,「それぞれの果たすべき役割」という文言があります。当然ながら市民の皆さんと市とはまちづくりにおいて役割が違うという前提の中で,「それぞれ」という言葉を用いています。
この部分が,前文に反映されているわけですが,「それぞれ」を抜くと,役割が一緒じゃないかと解釈される懸念もあったので,敢えて入れさせていただきました。
意見
委員
本日の審議事項ではないですが,議会の条項の取り扱いについて意見があります。
最高規範である自治基本条例の中に,市民,議会,市という三位一体の位置付けを規定してほしいと思います。市議会の方は,市議会で条例をつくられるとお聞きしていますけれども,やはり「市議会もこの自治基本条例をもとに取り組んでいただきたい」,と審議会の要望としたいと思っております。
やはり,「市民」「市議会」「市」の三者が揃ってまちづくりは進む,自治は進むと思います。
事務局
自治の推進は,市民,市議会,市という三位一体の関係があります。
市議会と市というのは,車の両輪にも例えられておりますし,議会条項が入らないと「自治基本条例」ではなく「行政基本条例」という形にならざるを得ないと考えております。
現在,議会の方では,研究会を立ち上げておられて,自治基本条例に挿入する「議会条項」の部分と「議会基本条例」というのを両方検討がなされております。
議会条項についての意見,要望を付帯意見として答申に盛り込むことも可能ですが,委員の皆さんの御意見をお聞きしたいと思います。
委員
議会条項について付帯意見をつけることで全委員一致。
審議会終了
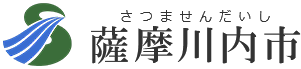







 メニューを閉じる
メニューを閉じる
更新日:2023年03月27日