薩摩川内市総合計画審議会[第6回] 会議録
1.開催日時
平成20年6月9日(月曜日) 10時00分~11時30分
2.開催場所
薩摩川内市役所本庁 401会議室
3.出席状況(敬称は省略)
[1]委員11名(欠席4名)
- 会長:黒瀬一郎
- 副会長:今藤尚一
- 委員:森薗正堂,谷口兼弘,三角文孝,米丸恭生,橋口史人,下野千代男,徳田勝章,齋藤佐千子,伊地知すみ子
欠席:山元浩義,田島直美,犬塚孝明,中村貴恵
[2]事務局等 5人
- 企画政策部長:桐原大明
- 企画政策課:課長 末永隆光,課長代理 古川英利,政策グループ長 有馬眞二郎,主任補 諏訪原智子
4.会次第
- 会次第
- 会長あいさつ
- 企画政策部長あいさつ
- 議事
- 審議第6号 薩摩川内市自治基本条例原案 修正案について
- 審議第7号 薩摩川内市自治基本条例原案 答申案について
- 閉会
5.配布資料
ダウンロード
6.委員から出された主な意見(要点・録音なし)
委員
第26条第4項についてお尋ねします。「市は,総合計画を策定する際は,広域的な観点から調整が必要な場合を除き,…」とありますが,ここで,「除外」を設けた意図をお聞きしたいと思います。
事務局
「広域的な観点」というのは,それぞれの地区コミュニティ協議会だけでなく,複数の地区コミュニティ協議会が取り組んでいかなければならない事業を検討する場合,あるいは,財政的な面も含めて市全体の計画として検討する場合です。1箇所の地区振興計画を尊重したがために,市全体として計画がまとめられないという自体になっては困るということです。
地区ごとの計画に齟齬が生じた場合,それぞれの地区が違う方向を向いた計画を立てた場合,市域全体の利益という観点から調整させてもらいます。また,財政的側面からも調整させてもらうことがあるということです。
「尊重する」という表現だけに留めてしまうと,市全体の調和を失う恐れもあり,市長が調整することも必要ではないかと判断しました。
委員
そのような意図であれば,「広域的な観点から調整をしながら尊重する」というフレーズがいいのではないでしょうか。
委員
このように,前面に「除き」という表現を用いると,受け取る方も構えてしまい,不信感みたいなものが生まれるのではないでしょうか。
事務局
ご指摘はもっともだと思います。では,第一義的に,まず「地区振興計画を尊重する」として,但し書きで,「広域的な観点から…」という修正ではどうでしょうか。
委員
文言の修正については,会長に一任いたします。
委員
第9条が3項から4項に増えています。そこの説明をお願いします。
事務局
第9条に関し,委員から出されたご意見が2つありました。
一つは,「まちづくりに携わる専門家」という表現。もう一つは「還元」という表現でした。これらは,共に第2項に入っていまして,そこを修正する必要がでてきました。そこで,より,わかりやすくということで,第2項を第2項,第3項という2つの項に分けて表現したところです。
委員
第20条に関しての質問です。条文中「生きがいの創出」「地域の創造」とありますが,一般的な表現ではないと思います。「生きがいづくり」とか「地域づくり」という表現に変えたらどうでしょうか。
事務局
自治基本条例は,市民にわかりやすくということで,表現に非常に苦慮しているところです。この「創出」「創造」は,これからのまちづくりに新たな概念を取り入れて,新たなものを起こしていくという意図で用いられています。
委員
条文の中の文言ですので,このままでもいいのではないかと思います。全部柔らかい表現に変えてしまうと条例の重みも失せていくと感じます。
大事なのは,我々が運用の中でこの言葉をどう解釈し,みんなに分からせるかということだと思います。
委員
同感です。
事務局
この条例に用いられる言葉の定義は,第2条に解説してありますが,外にも市民が読んだとき,理解しづらい言葉もあるかと思います。
この条例が施行された後には,分かり易い解説を踏まえたパンフレットを作成し,市民の皆さんに配布したいと考えています。
その中で,条文の意図,考え方とか分かりやすく説明したいと考えます。
委員
第17条に関しての質問です。「的確に対応」という表現がありますが,これは当たり前のことではないでしょうか。誠意を見せるのであれば,「速やかに」という表現でもいいのではないかと思います。
事務局
市民の皆さんからいろいろな要望,意見が行政には寄せられます。それらについては,解決のために努力はしているのですが,的確な対応がされていないという指摘もあっていろいろと問題とかトラブルが生じることもありました。
そこで,「速やかに」はもちろんですが,ここでは誠実に対応するということと,出された課題,苦情,それと要望,そのようなものに的確に対応するというのを前面に出したかったという思いがあります。
委員
第20条の「自主的に」という文言が入る位置の確認と,第2条を「ところによる」という表現に変更された理由を教えてください。
事務局
「ところによる」は,他の条例と合わせる形で変更しました。
感覚的な意見で申し訳ありませんが,「自主的に」を入れる位置はいろいろと考えましたが,この位置が一番馴染んだのでここに据えました。
委員
「自主的」というのは,受身でなく前向きに取り組むという意図ですよね。そうであれば,ランクは下がるような気もしますが「主体的に」という表現でもいいのではないでしょうか。
委員
コミュニティの中では,自分たちの責任において創造することが大切です。
そのような意味でも48地区それぞれの活動があると考えます。やはり,自主的に自分たちの地域のことは自分たち,地域住民が主体となって積極的に働きかけていく,課題を解決していくということが必要なのだと思います。
「自主的に」という表現は,条文の後ろにあってもいいのかもしれませんが,ここにあるからこそ,この条文の趣旨がはっきりするのではないでしょうか。できれば,この原案のままの位置がいいのかと思います。
委員
第24条です。「努めるものとする」の表現が気になります。コミュニティ活動あるいは,自治会加入に関して会の冒頭から問題になっているテーマなので,表現が気になりました。
委員
第4回の審議で,自治会に加入しない理由はそれぞれあるということで納得したところです。しかし,今後,条例を市民に周知し,みんなでやっていくということを目標に掲げているのであれば,ジレンマはあるのかなと思います。
委員
コミュニティ活動を行う立場の者からすれば,もう少し表現を強くしたいところです。「加入し」という表現があるために「努めるものとする」と整理されたと思うのですが,参加に関しては,「参加するものとする」とした方がいいと思います。
自治基本条例には罰則規定がないわけですから,「自治会に加入し,その活動に参加する」という表現でもいいと思います。
事務局
第24条の考え方をまず整理いたします。
自治会の加入率は約84%ということですが,逆に言うと16%入っていないということです。私どもとしては,自治会に加入していただいて自治基本条例の大きなテーマである情報共有,協働,参画というのを皆と一緒に行っていくということがベストだと思っております。
しかし,憲法第21条に「集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する」と規定されています。このような背景があって,強制加入は難しいと思っています。
「参加するよう努めるものとする」,「参加するものとする」という微妙な表現の違いではありますが,「参加するものとする」という肯定的な表現になると「参加しないといけない」という強制的意味合いを持つのではないか,という懸念がわいてきます。
委員
この問題は,非常に難しいですね。でも,この基本条例にこういった条文が入っただけでもいいのかなと感じています。
委員
今後は,それぞれですね,家族構成,年齢,生活そういったものを考慮して加入促進をはかっていく必要があろうかと思います。日常の会話の中でコミュニケーションを図りながら理解してもらうことが大切なのではないでしょうか。
委員
印象論ですが,第2章第5条です。「市民は,市政に関する情報の提供を受け,」「公共の福祉の増進のために」とあるんですが,規模が大きいように感じます。限定しなくていいでしょうか。
事務局
第11条に情報公開に関する条項があります。情報公開を行う際は,情報公開条例に基づいて行いますので,ご指摘の表現はこの中で整理されるのではないかと思います。
委員
第10条ですが,第1項から第3項までの順序がこれでいいのかなと思います。まず,情報提供を行うための体制整備に努めてから,提供すると考えますがどうでしょうか。
事務局
順序につきましては,第1項から情報共有,情報収集,体制整備となっています。まずは,市民と市の情報共有,これはまちづくりの3本柱の一つですが,そこから始めていって,市民に提供するための情報収集に努める。そして最後に体制といったものを構築するという順序の方が事務局としてはいいのではないかと思ったところです。
委員
自治基本条例の中で「支援」という言葉が多用されています。この言葉は,非常に便利で教育の現場でもよく用いられます。市が行う場合の「支援」とはどのようなことをお考えなのかお聞かせください。
事務局
この自治基本条例には市民の役割,事業者の役割,市の役割をそれぞれ規定していて3者は密接に結びついています。そこで,市が上からの目線で,指導するとか,補助するとか,そのような考え方ではなくて,市民と同じ立場でこの自治基本条例の趣旨を共有しながら,今後のまちづくりを進めていこうということが書かれています。強権的なイメージを払拭する「支援」という言葉を多用することにより,お互い対等なんだということ,皆と一緒になってまちづくりを進めていくんだということをアピールする意図があります。
委員
解説本は,高齢者にもわかりやすいものにしてください。
事務局
この条例は,子どもからお年寄りすべての人に関わる条例です。ですから,そこのところを配慮して,文字の大きさとか表現とか分かり易いものにしていきたいと思います。
委員
市民と市がそれぞれ対等な立場というのは,ありえないんじゃないかということで「対等な立場」を削除した経緯がありました。
そこで第34条「国,鹿児島県,市」の関係で対等はありえるのでしょうか。
事務局
地方分権一括法というのが制定されまして,地方自治法も改正されました。その中で,「国と地方公共団体は対等の立場です」という趣旨のことが規定されています。そこの部分を引用して「対等な立場」という表現を用いたところです。
委員
市民と市の関係も今後そのような方向に向かっていくということであれば,「対等な立場」という表現を復活させてもいいのかなと思いました。
これは,再審議になると思いますので,ひとつの意見として申しておきます。
薩摩川内市自治基本条例原案の修正案に関して,審議終了
委員
答申案について,このままこの案をもって本審議会の答申とすることで全会一致。
薩摩川内市自治基本条例原案の答申案に関して,審議終了
審議会終了
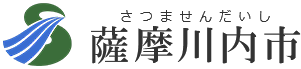







 メニューを閉じる
メニューを閉じる
更新日:2023年03月27日