医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証等)
医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合に、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すれば一医療機関における1か月のお支払いが自己負担限度額までとなります。
(補足1)保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなるため、同月に入院や外来など複数の受診がある場合は、高額療養費制度の申請が必要となることがあります。また、保険適用診療分が対象となるため、保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外です。
(補足2)自己負担限度額は所得により異なります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
限度額適用認定証の交付手続き
限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けるには、あらかじめ市役所窓口で申請手続きを行う必要があります。
申請窓口
本庁2階 保険年金課13番窓口、または支所 地域振興課
交付手続きに必要なもの
- 国民健康被保険者証またはマイナンバーカード(減額対象者のもの)
- (代理申請の場合)窓口来庁者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)
交付条件
- 申請時に国民健康保険税に未納がないこと
- (70歳以上74歳未満の場合)上記の条件に加えて、「世帯主および国民健康保険被保険者全員の住民税が非課税であること」または「被保険者証の負担割合が「3割」かつ課税所得が690万円未満であること」
(補足)70歳未満の方で国民健康保険税に未納があるとき、認定証の交付が受けられない場合があり、その際は「高額療養費費用貸付制度」をご利用いただきます。
申請書様式
限度額適用認定証申請書 (Excelファイル: 22.5KB)
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要です
これまで限度額適用認定を受けるには、あらかじめ限度額適用認定証等(以下、「認定証」という)の交付手続きを行っていただき、医療機関の窓口で認定証の提示が必要でしたが、マイナ保険証(健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。
利用方法:医療機関等の窓口でマイナ保険証または健康保険証を提示し、「限度額情報の表示」に同意する
手続きなしで高額療養費制度における自己負担額を超える医療費の支払いが免除されるため、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
(注意事項)
- 「オンライン資格確認」を導入していない医療機関・薬局では利用できません。対応している医療機関には「マイナ受付」のステッカーが掲示されています。
- 国民健康保険税の滞納がある方や、住民税非課税世帯の長期入院による食事代の減額を受けたい場合は市役所の窓口で手続き等を行う必要があります。
詳しくは以下のリンクをご覧ください
住民税非課税世帯で1年以内の入院日数が90日を超えた場合
入院した場合、食事負担額(標準負担額)は次のとおりとなります。
- 課税世帯:1食490円
- 非課税世帯:1食230円(70歳以上の区分1に該当の方のみ1食110円)
住民税非課税世帯(区分オ、区分2に該当)の方については、1年以内の入院日数が90日を超えた場合、申請により91日目からの食事代が230円から180円に減額となる制度があります。
申請に必要なもの
- 国民健康被保険者証またはマイナンバーカード(減額対象者のもの)
- (代理申請の場合)窓口来庁者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 入院期間が確認できる領収書や入院期間証明書(入院日数が90日を超えていることが確認できる書類)
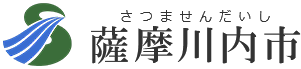







 メニューを閉じる
メニューを閉じる
更新日:2024年06月05日