特別児童扶養手当
1 特別児童扶養手当とは
(1)対象者
20歳未満で、身体または精神に重度又は中度の障害を有する児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
鹿児島県が決定し、手当を支給する制度ですが、申請書の受付や通知書の送付などの窓口は市役所で行っています。
手当に該当する障害の程度については、こちらをご覧ください 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3(pdfファイル)
ただし、次のいずれかに該当する場合は受給することができません。
1.児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
2.児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
3.児童が、児童福祉施設等に入所しているとき(幼稚園やこども園、療育施設への通所はこれにあたりません)
(2)手当の額
令和7年度分の手当額です。(消費者物価指数などにより、年度ごとに見直されることがあります)
| 区分 | 手当の額(児童一人あたりの月額) |
| 1 級(重度障害児) | 56,800円 |
| 2 級(中度障害児) | 37,830円 |
(3)手当の支払い
特別児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
手当の支払い時期は、毎年4月、8月及び11月の3回で、それぞれの前月までの分(11月は11月分まで)が支給されます。
| 支給対象月 | 支給月 |
| 12月分から 3月分まで | 4月 |
| 4月分から 7月分まで | 8月 |
| 8月分から 11月分 | 11月 |
(4)所得の制限
手当を請求する人(注1)・配偶者・手当を請求する人と生計を同一にする扶養義務者(注2)の前年(1月から6月までに手当を請求する場合は前々年)の所得が、次の表の所得制限限度額以上ある時は、その年の8月から翌年の7月までの手当が支給されません。
(注1)児童を父母がともに監護するときは、主として児童の生計を維持する人(収入の多い方)が請求者となります。
(注2)扶養義務者とは、手当を請求する人と生計を同一にしている父母、兄弟姉妹、祖父母、子、孫などの親族をいいます。
| 扶養親族等の数 | 請求者(本人)の所得額 | 配偶者・扶養義務者の所得額 |
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
所得制限額に加算されるもの
請求者本人の場合
(1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円加算
(2)特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は1人につき25万円加算
配偶者及び扶養親族の場合
(1)老人扶養親族がある場合は1人につき6万円加算(ただし、扶養親族すべてが老人扶養親族の場合は、1人を除く)
所得の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-8万円(社会保険料相当額)-以下の控除額(注4)
(給与所得または公的年金等にかかる所得がある場合は、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除)
(注4)
| 区分 | 控除額 |
|
障害者控除 |
270,000円 |
| 特別障害者控除 |
400,000円 |
| 寡婦控除 |
270,000円 |
| ひとり親控除 | 350,000円 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 |
| 雑損控除 | 地方税法による控除額 |
| 医療費控除 | 地方税法による控除額 |
| 小規模共済等掛金控除 | 地方税法による控除額 |
| 配偶者特別控除 | 地方税法による控除額 |
| 肉用牛の売却による事業所得 | 地方税法による控除額 |
2 申請・手続きについて
(1)認定請求
障害福祉課支援グループが申請手続きの窓口になります。市役所を通じて鹿児島県に認定請求書等が提出され、審査の結果により受給資格が認定された場合、手当が支給されます。
認定請求に必要なもの
1.認定請求書
2.戸籍謄本(請求者と児童が記載されているもの。請求者と児童が別の戸籍にある場合はそれぞれ1通ずつ必要です)(発行から1か月以内のもの)
3.特別児童扶養手当認定診断書(身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの場合は、診断書が省略できる場合がありますので、お問い合わせください)
4.各種障害者手帳(身体・療育・精神)(あれば)
5.振込口座申出書(請求者名義のもの)
6.請求者名義の通帳のコピー(振込口座申出書に金融機関の証明があれば省略できます)
このほかにも、児童と同居していない場合など、別に必要な書類がありますので、お問い合わせください。
(2)手当を受けている方の届出
手当を受けている方は、次のような届出が必要です。
| 所得状況届 |
受給資格者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出する必要があります。 届を提出しないと8月分以降の手当を受けることができません。また、2年間提出しないと受給資格が無くなります。 |
| 額改定届・請求書 |
障害の程度が変わったとき 対象児童に増減があったとき |
| 資格喪失届 |
受給資格が無くなったとき |
| 証書亡失届 | 証書をなくしたとき |
| 支給停止関係届 |
1 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき |
| その他の届 | 氏名・住所・金融機関口座を変更したとき |
届出が遅れたり、提出しなかったりすると、手当の振込が遅れたり、支給済みの手当を返還していただく場合がありますので、遅滞なく届け出てください。
(3)有期再認定請求について
特別児童扶養手当の認定を受けている方は、原則として、2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期までに、対象児童の診断書等を提出していただき、引き続き手当を受けられるかどうか、再認定を受ける必要があります。
正当な理由がなく提出期限内に提出しない場合は、再認定月の翌月から診断書の提出月までの手当の支給を受けることができなくなりますので、期限までに提出してください。
再認定が必要な月の1か月から2か月前までに、市役所から通知や診断書の用紙を郵送しますので、早めに病院の予約や手帳の更新をしてください。
診断書の作成年月日は手当の申請日または有期認定の提出期限日からおおむね2か月以内のものとしてください。
【再認定の結果、減額や資格喪失となった場合】
障害の程度が軽減していると認められるときは、1級から2級への減額改定または非該当(資格喪失)となります。
この場合、診断書作成日(ただし、有期後に診断書が作成された場合は有期年月)を基準として手当の減額改定や資格喪失の処分が行われます。
(例)7月有期の方が、5月20日に作成された診断書を提出し、再判定の結果1級から2級に変更となった場合
診断書作成日(5月20日)の翌月分(6月分)から2級と認定されます。
(例)7月有期の方が、5月20日に作成された診断書を提出し、再判定の結果、非該当となった場合
診断書作成日(5月20日)付けで資格喪失となります。手当は5月分まで支給されます。
(4)特別児童扶養手当認定診断書について
支給対象児童の障害の部位ごとに診断書の様式が定められており、市役所障害福祉課でお渡ししています。また、鹿児島県のホームページからダウンロードできます。
診断書の種類は以下のとおりです。
1. 眼の障害用
2. 聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用
3. 肢体不自由用
4. 知的障害・精神障害用
5. 呼吸機能障害用
6. 循環器疾患の障害用
7. 腎、肝疾患、糖尿病の障害用
8. 血液・造血器、その他の障害用
診断書の提出を省略できる場合
対象児童が以下の手帳を取得しているときは、診断書の提出を省略できる場合があります。
1. 身体障害者手帳の1級から3級(下肢障害の4級の一部を含む。内部障害や視野障害は除きます。
2. 療育手帳のA1またはA2
注意
基本的には身体障害者手帳の交付年月日または療育手帳の判定年月日が手当の申請日から2年以内のものが有効となりますが、2年間近であれば診断書の提出が省略できない場合などもありますので、詳しくは障害福祉課支援グループへお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 障害福祉課 支援グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
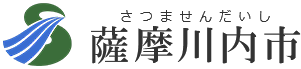







 メニューを閉じる
メニューを閉じる
更新日:2025年04月01日