薩摩川内SDGsチャレンジストーリー(#25-3 樋脇地区コミュニティ協議会)
薩摩川内市では、令和3年6月8日に、市長が「薩摩川内市未来創生SDGs・カーボンニュートラル宣言」を実施し、2030年SDGsの達成と2050年カーボンニュートラルの達成に向けて取り組んでいます。また、令和4年5月20日には、国(内閣府)のSDGs未来都市に選定され、今後さらにSDGs及びカーボンニュートラルの達成に向けて、「薩摩川内SDGsチャレンジ」を合言葉に市民総ぐるみで取り組むことを目指しており、持続可能な社会の実現のために、「薩摩川内SDGsチャレンジ」を合言葉として、一人ひとりができることからSDGsの達成に貢献し、市民のみなさんと一緒に薩摩川内市の未来をつくる各種取組を実施しています。
各種取組の1つとして、市内でSDGsに関連する取組を行っている市民の方をインタビューした「SDGsチャレンジストーリー」を動画及びWebコラムにて公表しています。今回は、樋脇地区コミュニティ協議会 会長の上床 博道さんをインタビューしました。
【関連ゴール】11 住み続けられるまちづくりを 15 陸の豊かさも守ろう

「共に学び、共に助け合い、幸福感を高める」
樋脇地区コミュニティ協議会では、これまでも丸山ウォークラリーや歴史散歩、餅つきや物産展、中学生の演奏会など盛りだくさんの内容に多くの人が集まるフェスティバルに、清掃活動や交通安全啓発運動など、さまざまな地域活動が活発に行われてきました。上床さんは、地区の伝統や特長はあるかもしれませんね、としたうえで「参加できる方は高齢者が中心ですが、地域の事業所、企業のみなさんも非常に協力的なのがありがたいですね。若い方たちがボランティアで参加してくれたり、ドローン撮影で協力してくれたりと助かっています。物心両面で地域活動を支えてくださっている」と感謝します。「協議会の役員が率先して、熱意をもって当たれば、多くの方が協力してくれる」ことを実感してきました。

一方で、地域の人口減少と高齢化が進んでいることは樋脇地区も例外ではありません。今後、どのような地域活動が望ましいのでしょうか。
「樋脇地区は自治会が42もあるんです。薩摩川内市のなかでも一番多い。現在、合併を進めているところです。地域をより強くするための合併です」と上床さんは言います。「小さい自治会で何が困るかというと、自主防災力が弱くなってしまうこと。備蓄用品、発電機など、いざという時のための備えは補助制度なども活用できるんですが、小さな自治会で会長が毎年変わるようなところでは、地域のビジョンが描きづらい。今後、合併を促進することで『共に学び、共に助け合い、幸福感を高める』ための活動も持続できるのです」と上床さん。『共に学び、共に助け合い、幸福感を高める』とは私が会長になって掲げたスローガンです、と照れながらも「人というのは助け合って、幸福感が高まるもの。そして何でも共にすることが大事。経済性ばかりを追求せず、みなさんの長所を生かし、できる限りいろんな声を聞いて、やっていきたいですね」と真剣な面持ちで語ってくれました。
「丸山もその手段のひとつ。すべては幸福感を高めるためです。みんなで集まって、整備する。一緒に汗をかいて頑張ったなあ、やったなあ、という達成感を得ることが何よりも大切です」と語る上床さん。その表情は地域を守り、暮らしてきた人ならではの慈しみに満ちたものでした。
2023年11月取材
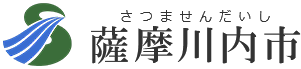







 メニューを閉じる
メニューを閉じる
更新日:2024年03月06日