広報薩摩川内9月通常版 キジカケル突撃レポート~日本遺産を巡ろう編~
本市に残る文化財などが日本遺産に認定されていることを知っていますか。日本遺産とは、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定するものです。本市では、2019年(令和元年)に認定された、「薩摩の武士が生きた町~武家屋敷群「麓」を歩く~」の構成文化財に「入来麓」、「里麓」、「手打麓」などが含まれています。
今回は、構成文化財となっている各麓の特徴や魅力を深ボリします。
麓とは
麓は、石垣、生垣で屋敷割りを行った武士の家が並んでいて、さまざまな工夫が凝らされた造りになっています。
現在、県内で日本遺産として登録されて残る麓の数は、12カ所。本市は、その中で最も多い3カ所が登録されています。

入来麓
川と山に囲まれた自然の地形をうまく利用した武家集落。2003年(平成15年)12月に国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されています。

ここは入来麓の中で、最も高い石垣。敵が登れないようにカーブがかかった「武者返し」という形になっているんだって!

入来麓の石垣の特徴

入来麓の石垣は、川の石を使用しています。上下に大きい玉石を置き、真ん中に小さい石をはさんでいます。1つの石を中心に、6から7つの石で囲んでいるのが特徴です。生垣は、石垣を傷めないよう根が垂直に伸びる茶の木などを使用しています。

この積み方を、野石乱積みというよ!
寝西郷


現在、入来小学校がある場所は、入来の殿様がいたといわれています。
入来小学校から麓の方を見ると、一番右側の高い山を枕に、西郷さんが寝ているように見えることから、「寝西郷」と呼ばれているんだって!
清色城跡の堀切
高さは約30メートル。人、1人分しか通れないため、攻めてくる敵を待ち構えて戦っていたといわれています。堀切を登った先から見える景色は絶景です。


堀切の中は夏場でも涼しく快適だけど、夏場は特にヘビが出ることもあるから気を付けてね。
里麓

里麓は海に面しており、海路の往来を監視するという役割を担っていました。海辺の丸い玉石を使った石垣が特徴的です。

近隣住民などが石垣の清掃を行い、景観を保持しているんだって!
里麓武家屋敷通りまで道案内

里港から徒歩5分。里みなと公園付近から石垣に沿って歩道に色が付けられています。
里麓武家屋敷通りまで道案内をしてくれます。
里麓の石垣の特徴

里麓の石垣は、主に台風や偏西風などから家を守るために作られました。
全体的に丸石の石垣が特徴的ですが、強度を高めるため、端には角張った大きな石が見られます。生垣は、庭木に実用的な果物の木も多かったようですが、武道で使う木剣として利用できる、硬いイスノキなどが多く植えられています。
亀城跡

現在の里小学校の裏にある「亀城跡」。山が亀の形に見えることから名付けられたといわれています。 鎌倉時代、地頭の小川氏の居城とされていました。

亀城跡を登ると、里の海を見渡せる絶景が広がっているよ!
石敢當

突き当たりの家の石垣には魔よけの意味を込めて、石敢當と呼ばれる石碑を置いています。沖縄や鹿児島を中心に残る石碑です。甑島でも見ることができます。
手打麓

薩摩藩は、江戸時代を通して、浄土真宗(一向宗)を禁教としました。手打麓の石垣は、信仰していることを役人たちに気付かれないよう工夫を凝らして作られたといわれています。

道幅は比較的広く、乗馬の練習をしていたといわれているよ!
手打麓の石垣の特徴

山から採ってきた石を積み上げた石垣が特徴です。外側と内側から積み上げ、土を詰めて生垣を植えている2層構造になっています。
津口番所跡

異国船の取り締まりのために置かれていました。近くの観音山を見張り山とし、取り締まりは番所の中でも特に厳しかったといわれています。
武家住宅の造り

武家住宅の造りは、敵などの侵入を防ぐため、入り口には石垣が盾のように置かれており、直接入ってこれないような構造になっています。また、家の中から外の様子は見ることができますが、外から中の様子を見ることはできません。
(注意)厠とは、家の外側に設けた現代のトイレのこと。

手打麓には、通行人同士が話している内容を盗み聞きするため、門口の道路沿いの左右どちらかに厠が作られていたんだって!
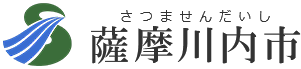







 メニューを閉じる
メニューを閉じる
更新日:2025年09月10日