薩摩川内SDGsチャレンジストーリー(#41-1 入来花水木会 ~入来麓に咲いた花、灯るかがり火~)
本市では、令和3年6月8日に、市長が「薩摩川内市未来創生SDGs・カーボンニュートラル宣言」を実施し、2030年SDGsの達成と2050年カーボンニュートラルの達成に向けて取り組んでいます。
また、令和4年5月20日には、国(内閣府)のSDGs未来都市に選定され、今後さらにSDGs及びカーボンニュートラルの達成に向けて、「薩摩川内SDGsチャレンジ」を合言葉に市民総ぐるみで取り組むことを目指し、持続可能な社会の実現のために、一人ひとりができることからSDGsの達成に貢献し、市民のみなさんと一緒に本市の未来を創る各種取り組みを実施しています。
各種取り組みの1つとして、市内でSDGsに関連する取り組みを行っている市民の方をインタビューした「薩摩川内SDGsチャレンジストーリー」を動画及びWebコラムにて公表しています。
【関連ゴール】11 住み続けられるまちづくりを

はじめに
薩摩川内市入来町浦之名。山城「清色城」跡と樋脇川に囲まれた一帯は中世の町並みを今に伝える「いりき」として、日本遺産「薩摩の武士が生きた町」のひとつに挙げられています。その歴史は鎌倉時代にさかのぼり、1247年、相模国渋谷庄の地頭であった渋谷光重に合戦の恩賞として薩摩国に所領が与えられると、その子孫が移り住み家名もそれぞれの地名にちなみ入来院、祁答院、高城、東郷鶴田と称して各地を治めてきました。江戸時代以降は島津氏の支配下に置かれましたが、入来院家は島津家との関係を深めるなどしながら明治維新を迎えました。
入来の名を一躍有名にしたのが、エール大学の教授、朝河貫一博士の研究により英訳された「入来文書」です。入来院家が代々記し伝えてきた「入来文書」は日本の封建制度を詳細に伝える資料として世界的に高い評価を受けました。

入来院 久子さん
入来花水木会のなりたち
この入来麓に魅了されたひとりの女性がいました。入来院貞子さんです。1994年、夫の重朝さんと入来に移り住むと、持ち前のバイタリティで町おこしに取り組み始めます。1998年に「入来花水木会」を立ち上げ、翌年には能楽師を招いて第1回「入来薪能」を開催。『貞子の語る入来文書』を上梓するなど、多くのエッセーを執筆しながら活動を続け、2010年の第7回「入来薪能」を終えた翌年、貞子さんは逝去されました。
その後、入来麓に着任した地域おこし協力隊と地域の人々の協働により、観光の目玉となる清色城「城郭符」の発行、入来院一族から島津貴久に嫁ぎ、島津義久・義弘・歳久の三兄弟を生んだ女性、雪窓院に着想を得た銘菓も誕生しました。茅葺門や旧増田家住宅など、入来麓の景観を活かした町歩きイベントをはじめ、お月見、「かえんそや」(桃の節句に女子がお菓子を持ち寄り交換する入来麓の風習)などの伝統行事も評判を集め、県内外より多くの観光客が訪れるようになりました。

まちあるき1
貞子さんの他界に伴い、一度消滅していた入来花水木会。思いを引き継ぎ、入来麓を盛り上げようと同会を再興したのが貞子さんの長女、入来院久子さんです。久子さんは平成29年に入来に移住し、「薩摩川内市伝統的建造物群保存地区保存審議会」の委員と「入来伝統的建造物群保存会」の役員として活動するうちに「入来武家屋敷群の素晴らしさを世の中にもっと広め、これからも素晴らしい入来麓の景観を守っていきたいという想いが沸き起こった」と熱く語ります。こうして令和3年、新生「入来花水木会」が誕生しました。鹿児島県地域振興局に「景観アドバイザー」の派遣を依頼し、助言を仰ぐことから始まった会の活動は「たのしいまち歩き」事業、美化清掃活動や文化講演事業へと発展していきます。
先人たちが守り残した武家屋敷群入来麓地区の景観や文化を守りながら、観光地として知名度を上げ、地区全体を活性化させるためには、時流を取り入れながらも慎重なかじ取りが求められます。活動を続けるにあたり大切にしていることを、入来花水木会のメンバーに聞きました。(インタビューの内容は#2、#3に掲載されています。)

まちあるき2
令和6年12月取材
写真(まちあるき1,2)入来花水木会提供
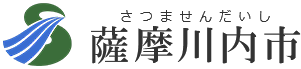







 メニューを閉じる
メニューを閉じる
更新日:2025年03月07日