薩摩川内SDGsチャレンジストーリー(#9-2 認定NPO法人じゃっど 帖佐 理子さん)
薩摩川内市では、令和3年6月8日に、市長が「薩摩川内市未来創生SDGs・カーボンニュートラル宣言」を実施し、2030年SDGsの達成と2050年カーボンニュートラルの達成に向けて取り組んでいます。また、令和4年5月20日には、国(内閣府)のSDGs未来都市に選定され、今後さらにSDGs及びカーボンニュートラルの達成に向けて、「薩摩川内SDGsチャレンジ」を合言葉に市民総ぐるみで取り組むことを目指しており、持続可能な社会の実現のために、「薩摩川内SDGsチャレンジ」を合言葉として、一人ひとりができることからSDGsの達成に貢献し、市民のみなさんと一緒に薩摩川内市の未来をつくる各種取組を実施しています。
各種取組の1つとして、市内でSDGsに関連する取組を行っている市民の方をインタビューした「SDGsチャレンジストーリー」を動画及びWebコラムにて公表しています。第9弾となる今回は、認定NPO法人じゃっど 帖佐 理子さんをインタビューしました。
薩摩川内SDGsチャレンジストーリー(#9-1 認定NPO法人じゃっど 帖佐 理子さん)
【関連ゴール】3 すべての人に健康と福祉を 4 質の高い教育をみんなに

3 すべての人に健康と福祉を

4 質の高い教育をみんなに
認定NPO法人じゃっど 帖佐 理子 理事長

「ラオスの子どもたちのために、何かしてあげたい」「じゃっど!」。1992年、「認定NPO法人じゃっど」(以下、じゃっど)は、そんなやり取りをきっかけに薩摩川内市を拠点として始まった。「学校でとなりの席の子がノートを忘れたら、自分のノートを一枚ちぎって渡しますよね。同じような感じで、東南アジアの途上国であるラオス人民民主共和国(以下ラオス)で学校保健に関する活動をしよう。子どもたちが健康に育ち、教育を受けられるように支援しようという目的で生まれました」と語る帖佐理子理事長。じゃっど30年の歩みは、まさにSDGsの精神を先取りして実行してきたもの。立ち上げの経緯やこれまでの活動、今後の目標について、帖佐理事長に話をうかがった。
SDGsの源流、小さな流れのひとつとして、じゃっど活動も始まった
帖佐理事長「最初の活動は私や夫の帖佐徹、現地の友人たちが手弁当で始めました。ラオス人のドクターが「学校に援助をしてよ」と言うので、ラオスの首都であるヴィエンチャン特別市の郊外にある学校に一緒に行きました。中に入ると、壁がゆらゆらしている。生徒の親がお金を出し合って、れんがを作って、木の壁をれんがの壁にしたが、芯が入っていなかったんですね。補強のための不足分の援助を行いました」
「次第に周りの人たちも活動に興味を持ち始めて、ラオス人ドクター、徹医師、オーストラリアからのWHOの医師、ロシアから来ていたユニセフの医師が集まり、話し合いをしました。そこで出たのは、建物をつくるのは簡単だけど、やっぱりソフト面を援助するのがいいんじゃない?ということ。知識というのはずっと持っていける。子どもたちに学校保健のソフトを渡すNPOをやろうと、じゃっどの方針が固まりました」
「その後、日本に帰国し、川内青年会議所(JC)がサポートをしてくれたラオスでの活動報告を行いました。以降、ラオス人ドクターや大学教授、ラオス保健相、教育省の官僚たちと公私ともにパートナーシップを築き、現地のじゃっど活動は彼らが担当してきました。なかでも長年、中心的なメンバーとして動いてきたのが保健相の官僚であったソムチット氏とコンサップ氏の夫婦でした。先生たちに保健教育をし、子どもたちに伝えよう。そのための教材を整えよう。学校に井戸やトイレをつくろう、というじゃっど活動が彼らの協力を得て、大きく動き出しました。先生たちはみな、プライベートな時間を割いて協力してくださいました。井戸ができた、トイレができた、そしたら次は手洗い運動をしよう!オリジナルで手洗いの歌(アナマイ・ソング:衛生の歌)を作り、歌唱コンテストも開催されるなど、広範囲に拡大することができました。保健衛生教育と併せて、栄養の充実にも力を入れました。当時はビタミンA不足で鳥目(夜に視力が落ちる)の症状を持つ人が多かったので、食用油を支給しましたが、翌日市場で売られているのを目にしたこともありました。今では笑い話ですが、思ってもみないことはたくさんありました」

スタディツアーでのひとコマ。ラオス料理にチャレンジ!
現地の事情に合わせて、衛生や栄養のことをわかりやすく学べる紙芝居をつくり実演したり、先生向けにそれらの教材の使い方を教えるセミナーも行った。これらの活動は、日本からラオスを訪問した学校の先生、保育士の先生たちが担当し、通訳は青年海外協力隊の人たちが協力するなど、多くの人がじゃっど活動に賛同し、協力をしてくれた。活動は順調に進んでいたが、10年が経ったころ、帖佐理事長はある危機感をおぼえたという。
帖佐理事長「このままでは金の切れ目が縁の切れ目だな、と(笑)。日本で集めている寄付金や助成金のおかげで活動が出来ているが、お金がなくなったら何もなくなってしまう。どうしたらいいだろう?と考えました。いろんな知恵を絞った結果、ラオスの学校教育のカリキュラムに、じゃっどが行っているような学校保健の授業を入れてしまえば、たとえじゃっど活動が終わったとしても、知識は継続して伝えられていく。そう思って、徹医師や保健相の人たちと一緒に、大臣がそのへんのレストランで食事したりしているので、そこに出向いて話をしに行きました」
保健相や教育省の大臣との距離感が近かったのも功を奏したという。熱意を持って話をすると、学校保健って何?と興味を持ってくれた。医師や看護師が言うのではなく、日ごろから接している学校の先生たちが子どもたちに衛生の話をすることが重要なんです、意味があるんです!と訴えた。時を前後して、NPOじゃっどはJICA(国際協力機構)の開発パートナーシップ助成金に応募し、採択された。ラオスにおける日常的な健康問題のひとつが感染症だ。なかでも「鉤虫」が体内に入り込み、肝臓から血を吸うことで貧血を起こす症例が後を絶たない。裸足で畑にいると足の裏から感染するので、草履を履くというシンプルな行為で状況は改善できる。まずは鉤虫に焦点を絞って、感染防止活動を行った。検便をして駆虫薬を配布する。お母さんに「鉤虫感染」の情報を伝える。顕微鏡を購入し、生徒の検便をして、寄生虫がいるかどうか調べる。ひとつずつやっていった。自分たちだけでは人力が足りないので、工夫をした。ラオスの検査技師養成学校に教材として顕微鏡を供与し、看護学生の授業、実習の一環として検査をしてもらうと、活動も進んでいった。
この「鉤虫プロジェクト」は、JICAに加えてWHO、ユニセフ、ラオス政府にも来てもらい、成果を報告した。
「学校の先生から子どもたちを通して、保健の知識が村じゅうに広がります!」と力強く発表した。この活動に影響を受け、JICAはラオスの健康に関するボードゲームを作成して配布した。じゃっどの活動やその成果は現地でも確かな評価を獲得していた。日本政府から文科省に派遣されていた京都教育大学の教授や、じゃっどのJICAプログラム遂行者としてラオスで活動した吉田いつこ氏らが、ラオスの教育省に働きかけた結果、教師養成プログラムに学校保健が正式に採用されることになった。
帖佐理事長「やったー!と万歳しました。これで、自分たちが活動を引き上げたとしても、システムの中に入ったから、学校保健は残る。ラオス政府や教育機関も巻き込んで、いろんなタイミングが重なって、後世まで続く成果をあげることができました」
(取材:2023年6月)

みんなでダンス!
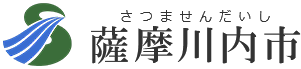







 メニューを閉じる
メニューを閉じる
更新日:2023年08月22日